| 浦上 |
荒木さん、続けて損保産業の民主化運動、「自由化」を要因とした合併・統合、組織問題を中心にお願いします。
|
行政・経営の政策・施策に対し
損保産業の健全性を守ってきた民主化運動
産業の社会的役割を果たすためには健全であれ
|
| 荒木 |
 労働組合と言えば、賃上げと長時間労働の改善といった労働者の処遇・労働条件の改善がその主たる役割というのが一般的な理解です。全損保にとっても当然、それは重要ですが、全損保の大きな特徴は、損保の社会的役割を果たすための産業の健全性を守ることを、結成時から方針の柱にあげとりくんできたことです。全損保第一年度運動方針六つの柱の一つに、『損保事業民主化』の具体的方策の推進を掲げ、時々の日本政府・金融行政、損保経営の産業や職場を歪めさせる政策の問題を指摘し、その改善を求め、対峙する姿で発揮されました。
労働組合と言えば、賃上げと長時間労働の改善といった労働者の処遇・労働条件の改善がその主たる役割というのが一般的な理解です。全損保にとっても当然、それは重要ですが、全損保の大きな特徴は、損保の社会的役割を果たすための産業の健全性を守ることを、結成時から方針の柱にあげとりくんできたことです。全損保第一年度運動方針六つの柱の一つに、『損保事業民主化』の具体的方策の推進を掲げ、時々の日本政府・金融行政、損保経営の産業や職場を歪めさせる政策の問題を指摘し、その改善を求め、対峙する姿で発揮されました。
1959年に保険審議会が設置され、1969年保険審議会答申では『自由化答申』と称され、『経営の効率化』『競争基盤の整備』『統一経理基準』などによる企業競争と内部蓄積の強化が求められました。この答申を受け企業間競争は激化し、商品の乱開発や「効率化」・販売督励の強化などが推し進められ、そのしわ寄せは従業員の働かされ方や長時間労働などとなって現れました。これに対し、全損保では、経営あておよび大蔵省あての要求にとりくみ、一つの例ですが、「76春闘対業界大蔵9項目要求」では、3項目に「不正常な募集・押し付け販売・労働強化を促進している『△△月間』『〇〇キャンペーン』等の年中行事化を規制すること」、4項目目には「代理店に対する裏表彰、社員に対する金品を伴う表彰を内容とする募集強化運動をやめ」などの改善要求を提出し、姿勢を正すように求めています。今であれば直ちに行政処分を受けかねないようなことが横行していました。これに輪をかけたのが、積立商品の販売です。長期総合から積立ファミリー、そして積立女性といった商品の拡販、とりわけ一時払いに偏重していきました。そして、積立商品傾斜のもとで不公正過当競争が一段と激化し『T・Y戦争激烈』『過当競争 秩序乱す』と新聞に報道されるまでになり、損保業界は無秩序で自浄力をなくした姿となりました。私自身の営業の経験でも、代理店・契約者に対して、「来月の加入でいい」という契約者に、「積立キャンペーン月なので今月入ってください」とか「一時払いでお願いします」と懇願し、はてには、クレジット会社や信販会社からお金を借り入れさせて一時払いへ誘導したりしました。契約者の意向は関係ないやり方です。また、上司は、「積立がとれるまで帰って来るな」と言い、職場にもどれば、成果がない社員には、貼りだされたキャンペーンの棒グラフにマークが付けられ、一番ひどいのはドクロマークが貼られるなど、まさにパワハラが当たり前におこなわれていた積立偏重が職場にもたらされていた歪みだったと思います。
|
積立保険の偏重政策が生んだ第一火災の破綻
|
| |
積立偏重の最も被害を受けたのは第一火災の仲間です。第一火災では、設立以来、大蔵省出身の社長が送り込まれ、積立重視の販売政策を展開していました。91年にバブルが崩壊し、積立から各社がかなり手を引いたなかでも、第一火災は売り続け、最終的には債務超過になって経営破綻に至りました。まさにこれは、大蔵省、損保経営の施策が引き起こした事態でした。こういったなかで、先ほどの76年の大蔵省要請もありますが、職場に、消費者に訴える運動を全損保はおこないました。91春闘では『消費者アンケート』にとりくみ、損保に何を期待しますかというアンケート結果では、消費者の多くが望んでいたのは「安価な保険料による幅広い補償」でした。積立じゃない、貯蓄じゃない、そのことを明らかにして経営に突きつけながら損保のあるべき健全な姿を求めてとりくんでいます。当時の私は営業職場にいましたが、そんな売り方に問題意識を持っていました。本部オルグで聞いた「積立偏重の問題」「拡販と運用の二つのペダルを踏み続けなければならない損保の姿」「いつか倒れてしまう」という問題指摘、組合の主張・とりくみに強く共感したことを覚えています。ちょっと話を戻しますが、自由化答申路線は、経営、大蔵省がやりたいことをやる、効率化を進めるという政策ですから、その実現に妨げとなる労働組合を敵視し、弱体化させたいと考えた経営の攻撃が1960年代の分裂を生じさせました。そして、全損保を再建した支部の組合弱体化を狙って行われた解雇・不当配転・賃金差別と闘ったのが住友闘争であり、東海闘争であり、富士闘争です。そして「合理化」という点では朝日闘争にもつながっていっています。
|
自由化に対し職場の声を土台に運動
|
| |
「自由化」がもたらした問題については記念誌に記載したとおりです。商品の乱開発と並行して特約がいっぱいでき、保険料率が上がったり下がったりするなかで、キャンペーンがおこなわれました。損害査定では24時間、365日、休日対応サービスなど、労働時間を「競争の具」とするサービス競争が進められました。そして、97年から2002年の5年間で、従業員は21,000人減り、代理店は375,474減るという大効率化が自由化の中で行われました。これに対して全損保は、自由化前の保険業法改定を受け、中執内に『民主化プロジェクト』を設置して分析・検証をおこない、支部地協代表者会議で産業の在り方を問うとりくみとして『損保20万署名』を提起し、一般消費者に署名を求め、産業はどうあるべきかを問いかける「民主化シンポジウム」を各地域、地協、地区協で開催しました。そして自由化以降は、『全損保緊急要求運動』、『職場からの問題提起』といった冊子の発行、シンポジウムの開催などにとりくみました。また、職場から実態を明らかにしていくということでとりくんだのが自由化以降、3回の「一人一言」運動です。そこには本当に生々しい実態がありましたし、組合員がどう思っているのか率直に、真剣に考えていることが明らかになりました。
|
労働組合の在り方は姿勢、考え方がカギ
|
| |
しかし、経営はそうしたとりくみをすすめる全損保を敵視し、弱体化を狙った攻撃をしかけてきました。それが、2000年以降の全損保の分裂・脱退です。結成60周年シンポジウムで全損保元委員長の瀧さんは、経営のやり方、脱退側の執行部が「一つの企業には一つの労働組合」という言葉を振りかざした経過を説明し、『労働組合の分裂は、経営者が経営者のために組織介入をしてきた時に起こります』と述べています。手法は60年代の分裂脱退と同じであり、不当労働行為の手法も同じでした。私も2000年秋に日本火災支部の分裂脱退を経験しました。当時、支部執行委員兼東京分会書記長でしたが、企業合併の相手である興亜火災には全損保興亜支部と多数派組合の興亜労組が存在しており、その両方と情報交換等を行なっていました。興亜火災の人事制度は成果主義制度で賃金格差が大きく、降格・降給もあるという制度でしたが、興亜労組の執行部は、「いい制度でしょう」と自慢げに話しました。これを分会委員会で報告したところ、「そんな制度を良いとする組合とは一緒になれませんね」というのが大方の受け止めでした。労働組合の在り方は、姿勢、考え方がカギです。職場もそのとおりだと受けとめていましたが、ひとたび分裂が表面化すると、泣く泣く、黙って、その分会委員たちも全損保を去りました。本当の労働組合のあり方を抹殺しながら進めていく全損保脱退のやり方だったと思います。あらためて、この損保産業の民主化は、経営、大蔵省のもたらした政策に対し、労働組合がしっかり方針を提起して、運動してたたかってきた歴史であったと言えます。
|
| 浦上 |
自由化が生んだ組織問題にも触れてもらいましたので、その当事者であった元日新支部委員長の管野さんからも発言をお願いします。
|
全損保こそ経営を追及できる唯一の組織
人員削減と軌を一にした全損保からの脱退
|
| 管野 |
 2014年7月に日新経営は「今後の将来ビジョン」を発表しました。その中では「2,500名体制から2,000名体制への移行」とした人員削減を公表しました。今考えると、日新経営は東京海上グループへの「ステージアップした効率化政策を推進するための新しい会社」をめざすために、全損保から脱退させることが必要だったのだと思います。旧執行部が全損保から「団体で」脱退するために臨時支部大会を開催することを発表した直後に、呼びかけ人7名で「全損保日新支部を守る有志の会」を発足させました。とにかく、不安でしたが、有志の会立ち上げの場には、全損保の多くの仲間が参加してくれ、その支援やカンパに勇気づけられました。有志の会の発足から再建大会までの2ヵ月間、どれだけの組合員を全損保に残すことができるのかが、課題でした。単独労組の日新労組では労働者の権利は守れないということを伝えるために、各地の出先職場や集会に出かけました。その結果、全損保本部には毎日のように「全損保にとどまる意思の確認書」が届き、何とか再建大会までに110名を超える仲間が結集してくれました。私は当時千葉の柏の職場にいましたが、今でもあの2ヵ月の経験が思い出され、ジンとくるものがあります。
2014年7月に日新経営は「今後の将来ビジョン」を発表しました。その中では「2,500名体制から2,000名体制への移行」とした人員削減を公表しました。今考えると、日新経営は東京海上グループへの「ステージアップした効率化政策を推進するための新しい会社」をめざすために、全損保から脱退させることが必要だったのだと思います。旧執行部が全損保から「団体で」脱退するために臨時支部大会を開催することを発表した直後に、呼びかけ人7名で「全損保日新支部を守る有志の会」を発足させました。とにかく、不安でしたが、有志の会立ち上げの場には、全損保の多くの仲間が参加してくれ、その支援やカンパに勇気づけられました。有志の会の発足から再建大会までの2ヵ月間、どれだけの組合員を全損保に残すことができるのかが、課題でした。単独労組の日新労組では労働者の権利は守れないということを伝えるために、各地の出先職場や集会に出かけました。その結果、全損保本部には毎日のように「全損保にとどまる意思の確認書」が届き、何とか再建大会までに110名を超える仲間が結集してくれました。私は当時千葉の柏の職場にいましたが、今でもあの2ヵ月の経験が思い出され、ジンとくるものがあります。
|
支部再建時の規模を維持しているのは職場に根ざした要求
|
| |
支部再建後も、日新労組とは組合財産分割問題があり、日新経営との間では、2つの組合に平等な労働協約の締結、団体交渉開催、組合事務室の獲得など課題は山積みでした。その後5年間で30名以上の支部組合員が退職等で会社を去りましたが、今なお支部組合員は再建時の100名以上を保っています。その力の源泉は、一人ひとりの組合員の頑張りと、職場に根差した要求を取り上げていること、それぞれが人間関係を大事にしていることにあります。また、当時から職場の要員不足はありましたし、地域型社員の処遇が低い、始業前の朝礼や勉強会に対する残業代が支給されないなどの問題に対し、職場の声を要求として掲げ交渉したことで成果をあげてきたことも支部への信頼を強めた理由だと感じています。人数では少数ですが、私たちが引続き全損保組合員であることの意義と存在価値は大きいものがあります。これまでやってきた活動を通して、全損保こそ職場に根差し、従業員を守って、経営を追及できる唯一の組織だと確信しています。日新労組が勝っているのは組合員の数だけです。会社政策の問題点を追及できていないこともこの5年で明らかになっています。
私は入社以来、全損保の青婦センターで育てられ、サマージャンボリーに参加して仲間と出会いました。支部再建の時も多くの全損保の仲間の力があって現在があります。日新支部は今後も全損保の一翼を支え続けます。
|
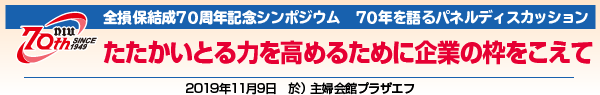
 労働組合と言えば、賃上げと長時間労働の改善といった労働者の処遇・労働条件の改善がその主たる役割というのが一般的な理解です。全損保にとっても当然、それは重要ですが、全損保の大きな特徴は、損保の社会的役割を果たすための産業の健全性を守ることを、結成時から方針の柱にあげとりくんできたことです。全損保第一年度運動方針六つの柱の一つに、『損保事業民主化』の具体的方策の推進を掲げ、時々の日本政府・金融行政、損保経営の産業や職場を歪めさせる政策の問題を指摘し、その改善を求め、対峙する姿で発揮されました。
労働組合と言えば、賃上げと長時間労働の改善といった労働者の処遇・労働条件の改善がその主たる役割というのが一般的な理解です。全損保にとっても当然、それは重要ですが、全損保の大きな特徴は、損保の社会的役割を果たすための産業の健全性を守ることを、結成時から方針の柱にあげとりくんできたことです。全損保第一年度運動方針六つの柱の一つに、『損保事業民主化』の具体的方策の推進を掲げ、時々の日本政府・金融行政、損保経営の産業や職場を歪めさせる政策の問題を指摘し、その改善を求め、対峙する姿で発揮されました。 2014年7月に日新経営は「今後の将来ビジョン」を発表しました。その中では「2,500名体制から2,000名体制への移行」とした人員削減を公表しました。今考えると、日新経営は東京海上グループへの「ステージアップした効率化政策を推進するための新しい会社」をめざすために、全損保から脱退させることが必要だったのだと思います。旧執行部が全損保から「団体で」脱退するために臨時支部大会を開催することを発表した直後に、呼びかけ人7名で「全損保日新支部を守る有志の会」を発足させました。とにかく、不安でしたが、有志の会立ち上げの場には、全損保の多くの仲間が参加してくれ、その支援やカンパに勇気づけられました。有志の会の発足から再建大会までの2ヵ月間、どれだけの組合員を全損保に残すことができるのかが、課題でした。単独労組の日新労組では労働者の権利は守れないということを伝えるために、各地の出先職場や集会に出かけました。その結果、全損保本部には毎日のように「全損保にとどまる意思の確認書」が届き、何とか再建大会までに110名を超える仲間が結集してくれました。私は当時千葉の柏の職場にいましたが、今でもあの2ヵ月の経験が思い出され、ジンとくるものがあります。
2014年7月に日新経営は「今後の将来ビジョン」を発表しました。その中では「2,500名体制から2,000名体制への移行」とした人員削減を公表しました。今考えると、日新経営は東京海上グループへの「ステージアップした効率化政策を推進するための新しい会社」をめざすために、全損保から脱退させることが必要だったのだと思います。旧執行部が全損保から「団体で」脱退するために臨時支部大会を開催することを発表した直後に、呼びかけ人7名で「全損保日新支部を守る有志の会」を発足させました。とにかく、不安でしたが、有志の会立ち上げの場には、全損保の多くの仲間が参加してくれ、その支援やカンパに勇気づけられました。有志の会の発足から再建大会までの2ヵ月間、どれだけの組合員を全損保に残すことができるのかが、課題でした。単独労組の日新労組では労働者の権利は守れないということを伝えるために、各地の出先職場や集会に出かけました。その結果、全損保本部には毎日のように「全損保にとどまる意思の確認書」が届き、何とか再建大会までに110名を超える仲間が結集してくれました。私は当時千葉の柏の職場にいましたが、今でもあの2ヵ月の経験が思い出され、ジンとくるものがあります。