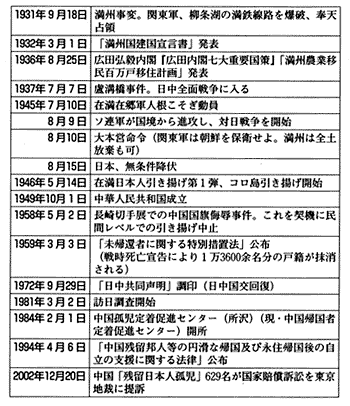|
|||
|
国民を棄てた国 その責任を問うたたかい 中国「残留孤児」の人権と尊厳の回復求めて |
||
|
宗藤泰而弁護士インタビュー 聞き手 全損保委員長 吉田有秀 |
||
|
| 三度の「棄民」の責任を問う | |
| 吉田) | この事件では、本質的には何が争われたのでしょうか。 |
| 宗藤) | 第一は、「残留孤児」を生み出した原因は国の政策に基くものであったかどうかということです。勝訴した神戸地裁の判決では、1932年、「満州国」建国以来、国が開拓民を「満州」に送り出した移民政策が始まって以来、ソ連軍が侵攻し、戦争が終わるまでの歴史的な事実を認定して、「自国民の生命、身体を軽視するまことに無慈悲な政策であった」ということを断定しました。 |
| 吉田) | 棄民政策と呼ばれるものですね。 |
| 宗藤) | それだけではありません。「残留孤児」は、ソ連軍が侵攻してきた混乱の中で、両親と死別したり、生き別れて孤児になりました。中国人に引き取られて、養子となって生きざるを得なかった。しかし、そのために、終戦の翌年から数年、集団引き揚げが行われた際に、帰国の機会が奪われてしまったわけです。その後は、東西の冷戦政策があり、1972年、実に戦後27年たって日中国交回復が成立した。それまで日本政府は何もせず、彼らは中国の地に放り出されたのです。その間に、侵略国日本の子どもとして差別され身を潜めるようにして、苦難の人生を送ったのです。「帰国させなかった」という不作為よりもむしろ積極的に帰国を妨害する措置をとったと神戸地裁の判決は認定しています。これが第二の棄民です。 |
| 吉田) | そしてようやく帰国となりますが。 |
| 宗藤) |
1980年代、戦後40年以上たって永住帰国が始まりましたが、年齢的に40代後半から50代ですから、日本語を覚えようとしてもできるわけがありません。日常の会話が不自由でない程度に日本語ができる人はおそらく1割に足りません。場当たり的で不十分な日本語教育によるものです。仕事もできず、最低限の生活も保障されませんでした。日本に帰ってきてからも充分な援助の手を差し伸べず、棄民したということです。これが第三の棄民です。 大まかに言えば、この三つの責任を裁判で明らかにしようと頑張ってきたということです。 |
| 判決が語った国の責任とは | |
| 吉田) | いま、政治的決着の動きが進められていますが、先生が担当された神戸地裁では勝利判決をかちとりました。 |
| 宗藤) | 神戸地裁の判決は、裁判官の気概が表れたすばらしい判決でしたが、主として国が控訴し、大阪高裁の裁判が始まりました。地裁のレベルでは神戸の他は7地裁で敗訴し、1勝7敗という状況でしたから、初めてとなる高裁レベルの勝訴判決を得たいと頑張っていたところです。7月の初めから政治的決着の動きが強まって、私個人も含めて全体としてどう総括していいのか、まだ定まらないと言う気持ちです。ただ、敗戦のとき13歳だった人は74歳になっています。政治決着により、できるだけ早く老後の安定をはかるという原告団の気持ちも強いと思います。 |
| 吉田) | 判決で求めていたことと、政治的決着の間の違いというのはどういうことでしょうか。 |
| 宗藤) | 裁判で求めていたのは、いわゆる「国の責任」です。「国の責任」はいくつかあります。残留孤児が長い間、国の棄民政策によって悲惨な苦痛、本当に苦難の人生を送ってきた。それに対する国の責任を明確にするというところが訴訟の大きな主眼でした。それと同時に、生活保護ではなくて継続的な給付金の制度によって老後の生活の安定をはかるべきだと。裁判では、この2つを目標にしてきたと言っていいわけです。ところが今度の政治決着は、主として老後の生活の安定をはかるという所にあって、謝罪がされていない。原告は、申し訳なかったと、みなさんを大変苦しい思いにおいたと、そういう謝罪がほしかったわけです。それが取れなかったということでいまなお不満であると考えておられる原告の方もおられるわけです。 |
| 吉田) | 先生自身は、この決着についてどう考えていらっしゃるのですか。 |
| 宗藤) |
まだまだ具体的支援策の細かいところについて、不明確なところがたくさんあり、厚労省や与党PTと交渉しなければいけないところがありますから、まだ総括が終わったわけではありません。しかし、率直にいって兵庫弁護団としては、ぎりぎりの決断で、決して大賛成で決意したわけではない。初めて支援策を受け入れると全国の弁護団が発表したときに、神戸でも記者会見をしたんです、原告も3人出席しましてね。「私たちは国に捨てられてきたんだ。その恨みは忘れません」とこういう状況でしゃべったんですよ。私も影響されて、ぎりぎりの決断であったと言わざるを得ませんでした。訴訟終結が本当によかったのか、私自身の結論も定まっていません。 具体的な支援策は、いろいろ細かい問題が残っていますが、住宅支援や医療支援、介護支援などの現物支給もあわせると、我々の要求と金額的には大きく変わりません。支援策を一日も早く実現されることを全国のたくさんの原告が、生活が大変苦しいだけに待ち望んでいることも現実です。 |
| 吉田) | 安倍首相が原告の方々と面会した際、「国を愛する気持ちが変わらなかったから、支援を遅らせてはいけないと考えた」と言っていたというので、複雑な心境になりました。 |
| 宗藤) | 神戸地裁の判決では、「日本に帰りたい」「自分の本当の親兄弟を知りたい」という願望は、人間としてのもっとも基本的、かつ自然な要求の発露に他ならない、と言い切っているわけです。こういってくれると、僕らもスッと、そうかと思うわけですね。「原告らも、上記のような人間としての自然な願望を長年抱き、最終的にはわが国に永住帰国したのである」と。だから安倍首相が「日本を愛している」というのとは、意味が違うんですよ。 |
| 吉田) | 国を愛するという真実味が違いますね。 |
| 宗藤) | この判決は、そこまで書くのかと思うほど、国の責任を鋭く指摘しています。例えば、身元保証がなければ帰国ができないと、なかなか帰れなかったある原告の例をあげ、「このような例に接すると、わが国は同胞に対して冷淡過ぎるのではないかという思いを禁じえない」と書いています。 |
| 吉田) | 判決にそこまで語られているのですか。 |
| 宗藤) |
一番僕が「これは」と思ったのは、先ほども触れましたが、国の責任に関して「戦後の憲法が立脚する価値観にたってみたときに、戦闘員でない一般の在満邦人を無防備な状態においた政策は自国民の生命、身体を著しく軽視する無慈悲な政策であったと言う他はない。したがって憲法の理念を国政の拠り所にしなければならない戦後の政府としては、可能な限り無慈悲な政策によってもたらされた自国民の被害を救済すべき高度の政治的責任を負うものと考えなければならない」としたところです。これがこの判決の拠って立つ根本的な理念であり、すばらしいところです。 |
| 国の冷たさと戦争責任 | ||
| 吉田) | それにしても、この国は、なぜ、国民にそんなに冷たいのでしょうか。 | |
| 宗藤) | 日本がまだ戦争責任を、外に対して十分にとっていないように、その裏返しで、自国民に対する戦争責任をとっていないということが大きな原因ではないでしょうか。北朝鮮の拉致被害者への支援と比べても大きな違いがあります。神戸地裁の判決は、残留孤児に対する支援の程度が、拉致被害者に対する支援の程度より「低くてよいわけがない」と言っています。なぜなら、北朝鮮の拉致被害者は、拉致されたことについて国に直接の落ち度があるわけじゃない。「残留孤児」は、国に落ち度があるからこういうことになった。支援の程度について拉致被害者よりも中国残留孤児の被害者の支援の程度が低いのはおかしいのではないか、というのが判決の考え方にあるわけです。 | |
| 吉田) | 今後に向けてどんなことを残留孤児の方にしていかなければいけないのでしょうか。 | |
| 宗藤) |
また、兵庫の場合には幸いに「支援する会」が出来て、生活講座を開いて「残留孤児」の方と交流するとか、してもらっています。「残留孤児」の人たちは、訴訟を通じて団結しましたが、これからも交流できる機会をつくることや、もっと日本社会に馴染んでいけるように努力する必要があります。一応の経済的な安定をはかることができても、日常生活、精神的な面で孤立しないで、日本社会に溶け込んで生きていけることが、安倍首相も言っている「尊厳をもって生きる」ということだと思うのですが、多くの課題は今後に残されています。 |
|
| 二度と悲劇おこしてはならない | |
| 吉田) | 戦時下の日本が今に連続しているということを痛感します。憲法改悪や「戦争をする国」への動きにつながっているのでしょうか。 |
| 宗藤) | 戦争に対する責任が足らないから、再び戦争をしようということについて、あまり抵抗感がないのだと思うのです。東京大空襲の被害者の戦争裁判が東京地裁で始まりましたね。非常に注目しているのですが、あれは日本の国民に対する戦争責任の問題を問う裁判です。「残留孤児」の人たちは中国に放り出されてそこで凄惨なことが起きたのですが、東京大空襲の問題は日本に生活をしていた国民が戦争によって受けた被害でしょう。戦争責任をどう自覚するかということと、憲法改悪などにどういう態度を取るのかは直結していると言う気がします。 |
| 吉田) | 先生がこの問題にかかわられた動機はどこにあるのですか。 |
| 宗藤) | 私は、ちょうど「残留孤児」と同じ年齢で、昭和7年、1932年、満州国建国の年に生まれているのです。それも、この問題に関わろうとした一つの大きな動機であることは間違いありません。責任者を頼まれたときに、ほとんど知識もなかったのですが、お役に立とうかと思ったのは、そこですね。自分自身があらためて戦争責任を考えてみようということになったということです。その一助として弁護団活動に参加しようと考えてみようと。そういうことだと思います。 |
| 吉田) | 裁判を通じて、どんなことが印象に残られていますか。 |
| 宗藤) |
一番感じたのは、日本にいながら日本語ができないために、人間としての生活が疎外される、被害の甚大は大変だということです。そういう意味では意思疎通は困難だったのですが、兵庫の場合は幸いにして原告団と弁護団との信頼関係が強かった。顔見たらわかる。やっぱり顔で判断するから。信頼が強い、それは非常にうれしかったですね。それが一つですね。 もう一つは、我々の問題で言えば、なんといっても神戸判決はうれしかったということですね。この判決くらい裁判官の気持ちと気概が表れた判決はないと思いますね。地裁では1勝7敗でしたらから、大阪高裁では、国側は負けた裁判の判決をばーっと出してくるのです。僕は、「この神戸判決には残留孤児を救済しなきゃいけないという裁判官の気概が表れているんだ。逆に言うと他の裁判所は気概がなかったということじゃないですか。どうか大阪高裁も、神戸地裁と同じような気概で判決をしてほしい」と訴えたのです。弁護士生活は長くありませんが、これまで判決で一番うれしかったのは、この神戸判決じゃなかったですかね。 3番目に、裁判をやったから原告団も団結できて、十分か不十分かは別にして、政治的決着を生み出す状況ができたということです。 |
| 吉田) | 最後になりますが、全損保の組合員にメッセージを。 |
| 宗藤) |
やはり、戦争の悲惨さ、戦争は悲劇を生むということでしょうね。原爆症の問題も、「残留孤児」の問題も、戦争の悲劇としか言いようがないですよね。二度とこういう人たちをつくってはいけないということです。
それと、訴訟を通じて国民の人に、「残留孤児」のだいたいの概念はわかったと思うのですね。直接に、みなさん一人ひとりに支援をしていただく必要はありませんが、残留孤児の人たちが身近におられたら援助を与えてあげてほしいと思います。 |
|
中国「残留孤児」国家賠償請求事件とは 中国「残留孤児」とは、終戦時に中国東北部(旧「満州」)で肉親とはぐれ、中国の家庭で育てられ、かろうじて中国で生きながらえた子供たちです。そのうち、約2400人が日本に永住帰国を果たしています。しかし、帰国した「残留孤児」たちの多くは日本語をよく話せません。「残留孤児」たちは高齢化し、生活苦のため、その7割は生活保護の受給者です。「残留孤児」たちの苦しみは、日本の満州侵略、終戦時の民間人遺棄、戦後の処置、そして帰国後の冷酷な処遇、つまりはすべて国の政策に起因しています。その責任追及と人権の回復を求めて立ち上がったのが、中国「残留孤児」国家賠償訴訟なのです。 1800人以上の「残留孤児」たちが、全国16の地方裁判所で提訴し、裁判は進められました。昨年12月1日、神戸地裁(宗藤弁護士などが担当)で画期的な勝訴をかちとったほかは、6つの地方裁判所で不当判決となりましたが、たたかいのなかで、与党に要求の水準を踏まえた支援策を提示させ、立法化への動きが進められています。 残留孤児が生まれたわけ 「残留孤児」を生んだ元凶は、戦前に国策としてとられた「満州移民政策」です。国は、開拓団民として32万人余の日本人を「満州」に移民させましたが、敗戦が濃厚になると、開拓団民をソ連侵攻への盾としました。そして、1945年7月には開拓団民のうち大半の男性(18歳以上45歳未満の男子25万人)を、関東軍(満州を守備していた日本軍)に「根こそぎ動員」したため、終戦前後には各地の開拓団は、老人・女性・子供たちだけになりました。 その上、ソ連参戦を知った関東軍が早々に撤退したため、開拓団民はソ連軍の侵攻(1945年8月9日〜)の前に無防備で置き去りにされたのです。 このように、わが国の指導者たちは、終戦前後、これら開拓団民を救うどころか、「満州」に置き去りにするという方針をとりました。 その結果、終戦前後の「満州」では、残された開拓団民が大量の難民となり、極寒の下で飢えにさらされ、あるいはソ連軍による殺戮、強姦、強盗や、日本の占領過程で人命や財産を奪われた中国人の報復による殺戮や強奪が行われました。さらに、関東軍兵による開拓団民らの遺棄、殺害さえ起こり、「集団自決」の強要という地獄図が繰り広げられました。 中国「残留孤児」たちは、このような惨劇の中で、生み出されたのです。 (以上、一部除き、兵庫原告団パンフレットより作成)
|
| このページのTOPへ |
 宗藤泰而弁護士
宗藤泰而弁護士